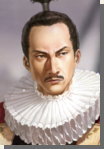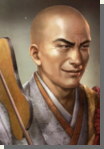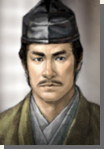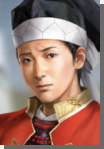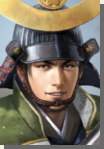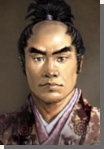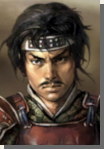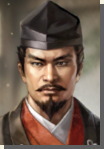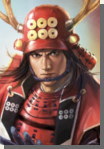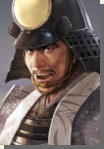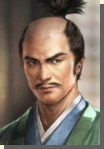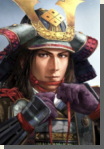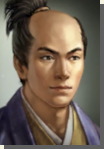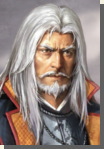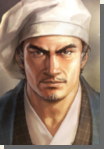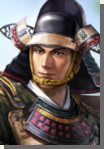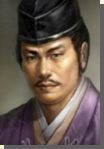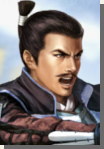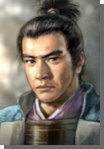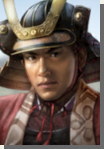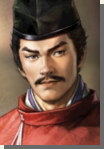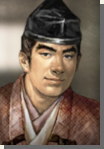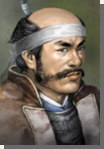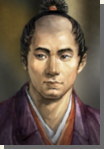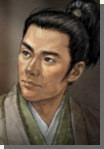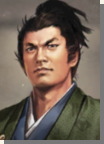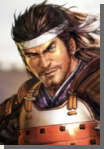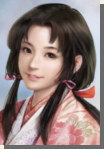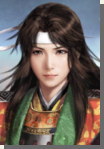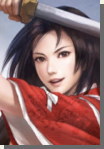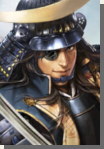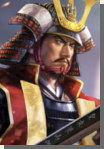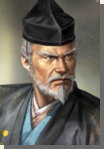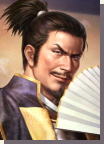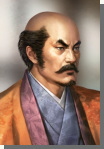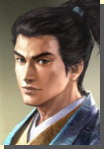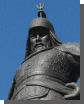伊達 政宗 (だて まさむね)
奥羽の独眼竜
1987年のNHK大河ドラマ「独眼竜政宗」の大ヒットで戦国のスーパースターとなった奥州の伊達男。
眼帯を付けた中二病心をくすぐる甘いマスク、数々のDQNで破天荒な逸話を持つ、戦国末期に強烈な印象を残した東北地方を代表する戦国大名である。
元は米沢周辺(山形と宮城の南部)の大名であった伊達家は、元々大きな勢力だったのに加え、政宗の曾祖父「伊達植宗」の婚姻外交により周辺の勢力を友好的に従属させており、政宗の祖父「伊達晴宗」の頃には東北地方を治める「奥州探題」にも任命され、名実共に奥羽の筆頭となっていた。
政宗の父「伊達輝宗」もその外交政策を継承し、この伊達家の統制により、東北地方は戦国時代になっても比較的安定した状態が続いていた。
しかし伊達家の内部では植宗と晴宗の対立、晴宗と輝宗の対立、さらに重鎮である中野宗時と輝宗の対立などがあり、平穏というわけでもなかった
1570年、織田家と浅井・朝倉家が戦っていた頃に、東北地方でも勢力争いや内紛が続発。
政宗の父・伊達輝宗は権勢を振るっていた中野宗時を追放し、実権を掌握すると、各勢力の調停に乗り出すが、東北も遅れてやって来た戦乱に飲み込まれていく。
伊達政宗が伊達家を継いだのは1584年。
すでに「本能寺の変」で織田信長が死去し、豊臣秀吉がその後継者になりつつあった頃だった。
幼い頃に病気(天然痘)によって片目を失い、すでに独眼となっていた。
伊達政宗が家督を継いですぐ、家臣の大内定綱が会津(福島西部)の大名「蘆名家」に寝返る。
政宗はこれを許さず、大内領にあった小手森城を包囲して陥落させ、そして女子供も含め、城内にいた500人を皆殺しにする「小手森城の撫で切り」と呼ばれた虐殺を行う。
恐れをなした大内定綱は防戦をあきらめて逃亡し、陸奥安達(福島中部)の大名「二本松家」に逃げるのだが、政宗は二本松の城を包囲。
そこで二本松の城主「畠山義継」は政宗の父・伊達輝宗に和平の仲介を要請し、輝宗もこれに応じて交渉に行くのだが、最初から策略だったのか、それとも近付いて来た政宗軍に恐れをなしたのか、畠山義継は帰宅しようとする輝宗をいきなり捕らえ、伊達軍に追い付かれると輝宗を人質にして逃げようとした。
ここで輝宗が「構わん!撃て!」と叫び、政宗が涙ながらに敵もろとも父を銃撃するシーンは、伊達政宗を扱った物語では前半の山場である。
怒りに駆られた伊達政宗はすぐに復讐戦(人取橋の戦い)を挑むが、常陸(茨城)の大名「佐竹家」が二本松に援軍を派遣、兵力に劣る伊達軍は惨敗し、政宗自身も銃撃されてしまう。
重鎮・鬼庭左月斎(良直)の奮戦で生還するも、鬼庭は戦死した。
翌年、傷の癒えた伊達政宗は再び二本松家に進攻。
もはや抗しきれないと悟った二本松は、陸奥相馬(福島東部)の大名「相馬家」に仲介を要請し、城を明け渡して蘆名家に亡命。
これで二本松は滅亡し、一旦騒動は落ち着くかに見えたが…… 1年も経たないうちに蘆名家の幼い跡継ぎが病死する。
そしてその跡継ぎを佐竹義重が自分の子にしようとしたため、再び争乱となる。
その翌年、天下を掌握しつつあった秀吉は私的な合戦を禁止する「惣無事令」を出すが、もはや東北勢は聞き入れない。
出羽最上(山形北東)の大名「最上家」の煽動で伊達家に従属していた「大崎家」が独立を画策、これを止めようと伊達政宗は進軍するが、逆に最上勢の反撃に遭う。
さらに相馬家が蘆名家と結んで伊達領に進攻し、戦乱は拡大。
だが、伊達政宗の母であり最上義光の妹でもある「義姫」の懇願もあって伊達と最上が停戦すると、政宗は相馬家の城を奇襲して混乱させ、その隙に蘆名軍(佐竹派)との決戦「摺上原の戦い」に挑み、これに勝利。
伊達家は蘆名領であった会津を支配した。
だが、伊達政宗にとって、ここがタイムアップであった。
その年(1590年)に豊臣秀吉は北条家へ進攻する「小田原征伐」を実施。
東北勢にも参加を求め、そして「お前ら勝手に合戦すんなって言っただろうが! 続けるようなら北条の次はお前だオラァ!」と通達。
伊達政宗は最初は渋っていたが、側近の片倉景綱の「秀吉はハエのようなもの。追い払ってもキリがない」という進言と、秀吉の家臣(和久宗是)からの再三の催促もあって、従うことを決意。
このとき、死の覚悟で訪れたことを示すため、白装束で秀吉の前に現れ、派手好きの秀吉に許されたという。
なお、この直前に最上義光が妹の義姫に「このままでは伊達家は秀吉に滅ぼされる。政宗を殺し、弟の小次郎に跡を継がせるべきだ」とささやき、母により毒殺されそうになったと言われている。
こうして伊達政宗は秀吉に従属するが、まだ領土拡大の野心は捨てていなかった。
会津を没収され、そこに蒲生氏郷が赴任するが、その蒲生氏郷と領地を巡って度々対立、暗殺しようとした説もある。
そして「葛西大崎一揆」と呼ばれる一揆を煽動し、蒲生氏郷と一揆勢を戦わせつつ、その領土を奪おうとした。
この一揆を煽動した件は蒲生氏郷に見破られ、秀吉に報告されるが、密書の花押(サイン)をちょこっと変えていたことと、白装束に加えて金の十字架を担いで弁明に向かうパフォーマンスで難を逃れている。
朝鮮出兵の際にも十字架を先頭に、将兵に絢爛豪華な衣装を着せて行軍し、見物した人々の話題となった。
これが派手な衣装を着こなす人を指す「伊達男」の語源になったと言われている。
「関ヶ原の戦い」では上杉軍の攻撃を受ける最上家に救援を送るが、その一方で領土拡大を狙って南部家(青森・岩手の大名)の一揆を煽動、後でバレて家康に怒られている。
以後もイスパニア(スペイン)との通商を計画してガレオン船を建造しヨーロッパに「遣欧使節」を派遣したり、大坂の陣で味方を銃撃して友軍の水野勝成と同士討ちしたり、将軍に食事を運んだとき幕臣が毒殺の危険を告げると「謀反するなら戦を起こすわ!毒なんか使うか!」と言って周りをギョッとさせたり、幕府の老中に唐突に相撲を挑んで開幕で張り手して大騒動になったり、エピソードを挙げていくとキリがない。
大坂の陣での挙動がおかしかったこともあって、最後まで天下を狙っていたとも言われている。 |